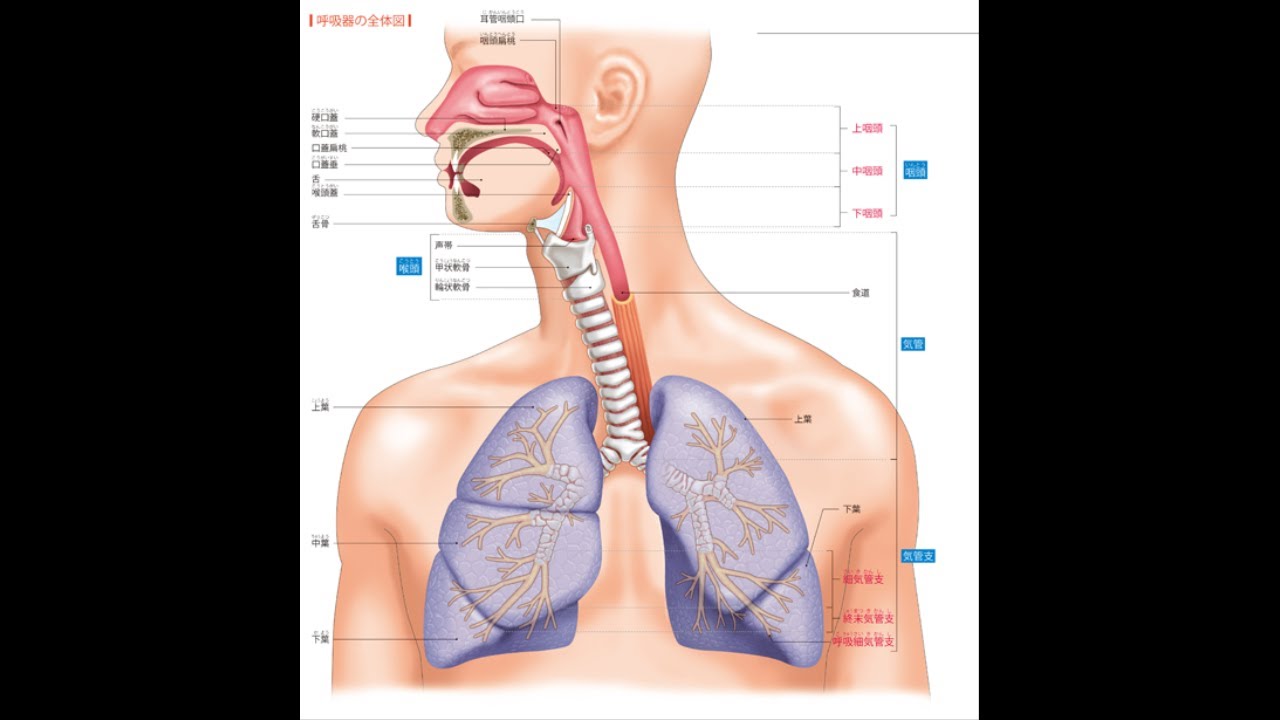「アヒルの代金を支払う」はポルトガル語でよく使われる表現で、「何かの責任を負う」、または他人によって引き起こされた特定の状況の結果を負担するという意味で使用されます。
「アヒルに金を払う」というフレーズは慣用的な表現、つまり、自分を馬鹿にしたり、答えるべきではないものに答えたり、お金を払ったりする行為を指す比喩的な意味を持っていると考えられています。
例:
少年は戦いを見守っていたが、結局代償を払うことになり、警察に逮捕されたのはただ一人だった。
兄弟が家をめちゃくちゃにし、その代償を私が払いました。
表現の由来
「アヒルに金を払え」という表現の起源を説明する正当な理由は 2 つあります。1 つ目は 15 世紀の物語への言及であり、もう 1 つは古いポルトガルのジョークです。
話によると、ある農民がアヒルを連れて通りを歩いていました。彼は動物を買いたいがお金がない女性からアプローチを受け、「性的好意」で代金を支払うと申し出た。
しばらくして、女性はアヒルの代金を支払うのに十分なセックスをしたと主張しましたが、農民はアヒルのためにもっと要求しました。女性の夫が家に到着すると、二人が口論しているのを発見し、喧嘩の理由を尋ねる。妻は、お百姓さんは買ったアヒルのためにもっとお金が欲しかったと説明します。夫は、さらなる議論を避けるために、文字通りアヒルの代金を支払うために農民にお金を提供します。
この表現が生まれたもう 1 つの考えられる理論は、ポルトガルで行われた古いゲームに由来しています。アヒルが木に縛り付けられ、参加者は馬に乗ってアヒルを繋いでいたロープを斧の一撃で切らなければならなかった。それができない場合、参加者はアヒルの代金を支払い、勝者にそれを提供しなければなりませんでした。
どちらの物語も、日常生活において「代償を払う」という表現の意味を、お金を支払って、何の利益も得られないものとして構築するのに役立ちました。
英語では、「アヒルにお金を払う」という表現は、「鞭打ち少年」または「缶を運ぶ」と翻訳できます。
例:
教師たちは、社会が自ら作り出す問題のために鞭打ちの少年にされることにうんざりしている。 (教師たちは社会が引き起こす問題の代償を払うことにうんざりしている。)
彼女は再び缶を持ち歩かなければなりません。
参考画像一覧

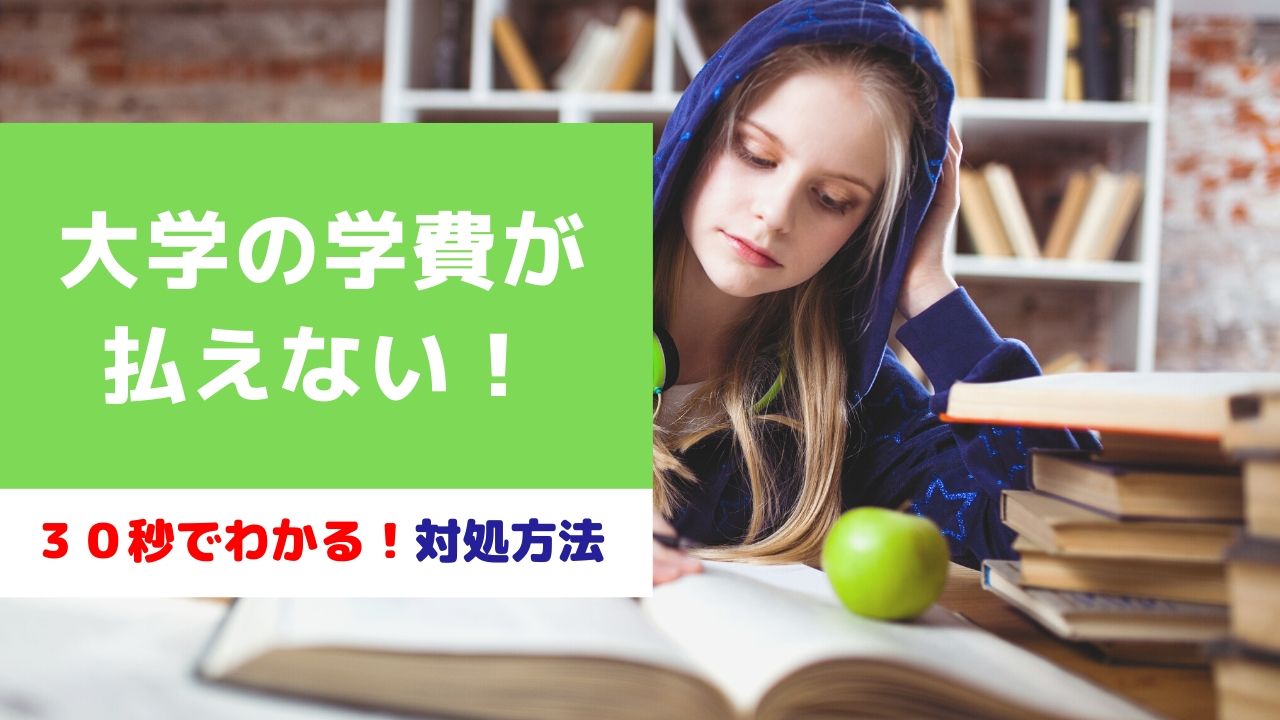
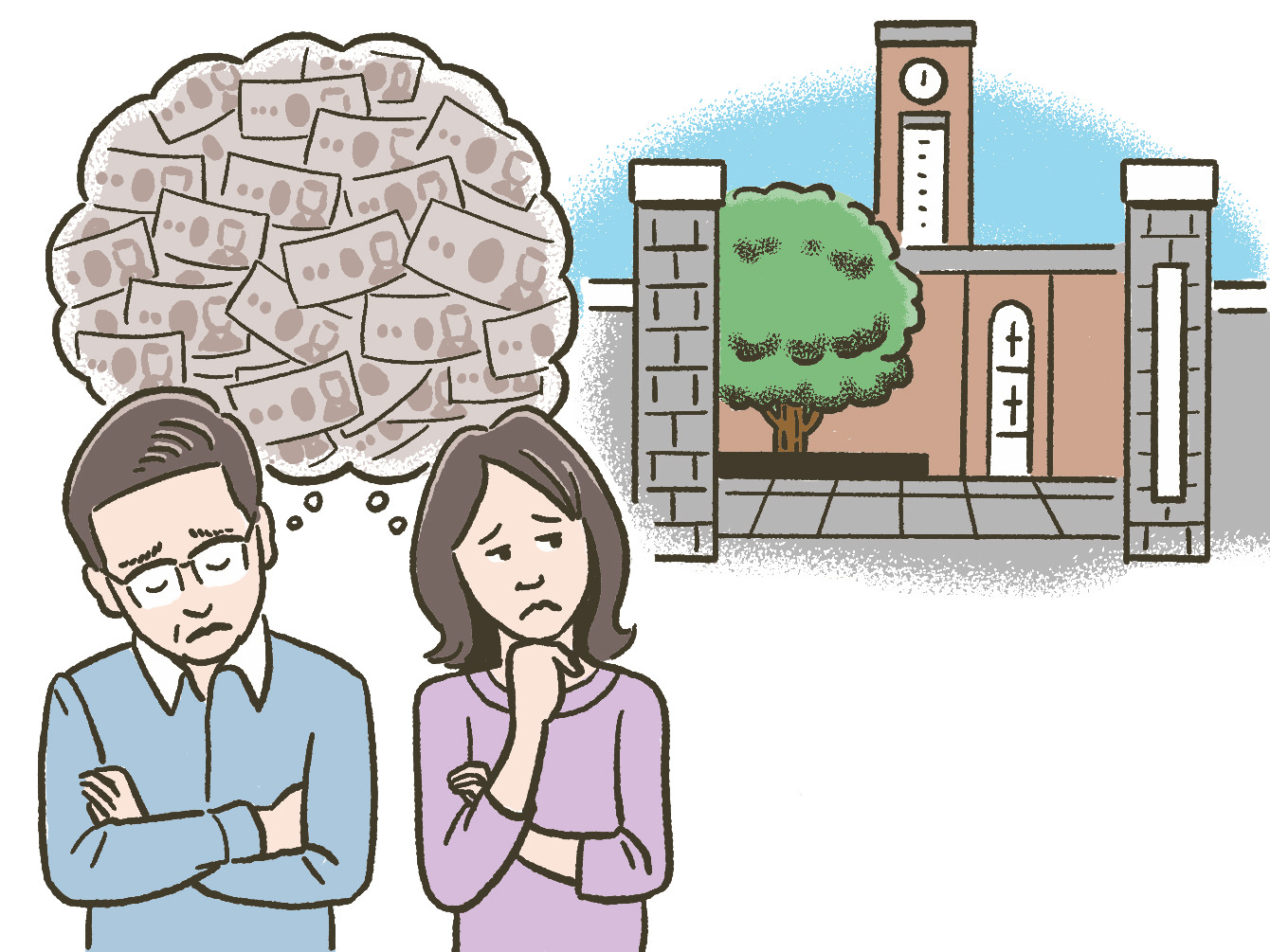
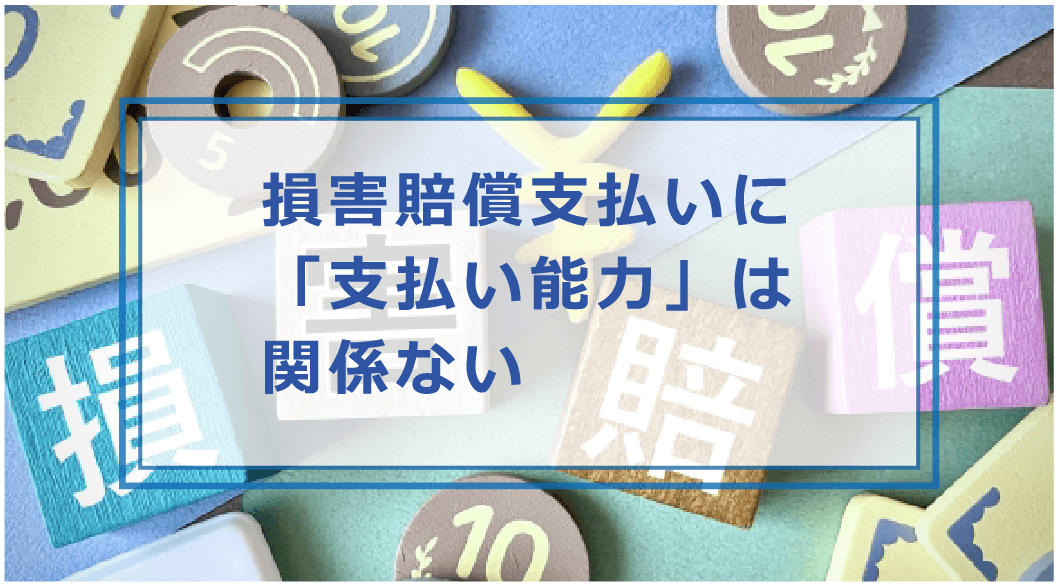






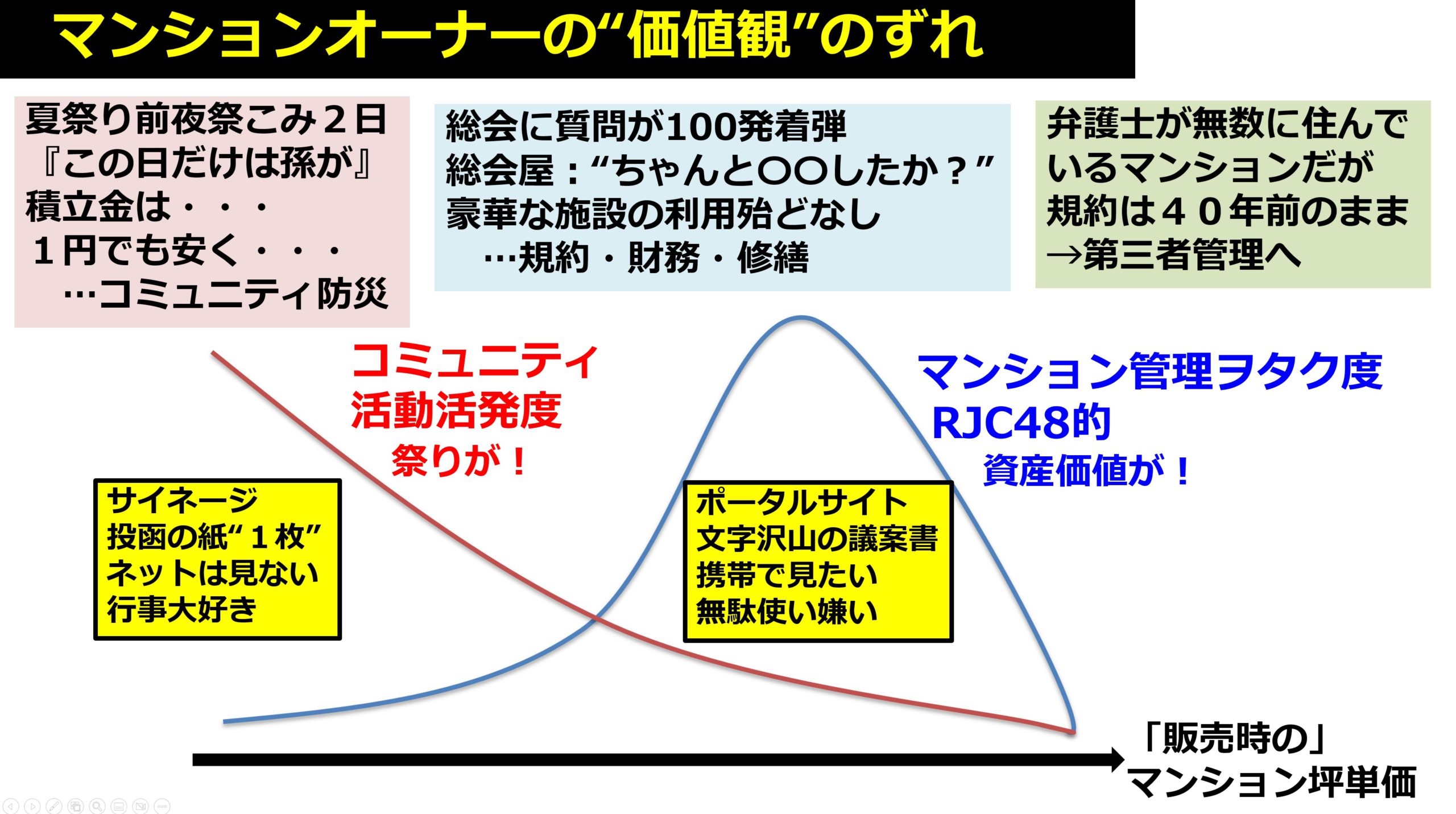
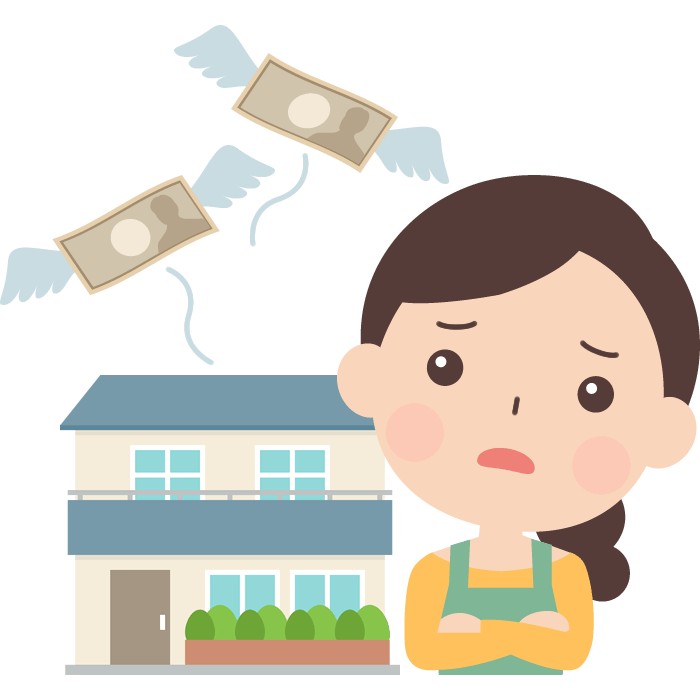

)

参考動画一覧
Aflac – 歌のショー (2000s, 日本)
手遊び歌「あひるはグワグワ」をしました
Goose Goose Duck | なんかアヒル人狼なのかな? 【にじさんじ/叶】
【衝撃の実態】6年間無休で働かされる絶世の美女達が大量にいる北朝鮮国営レストランに潜入。inラオス