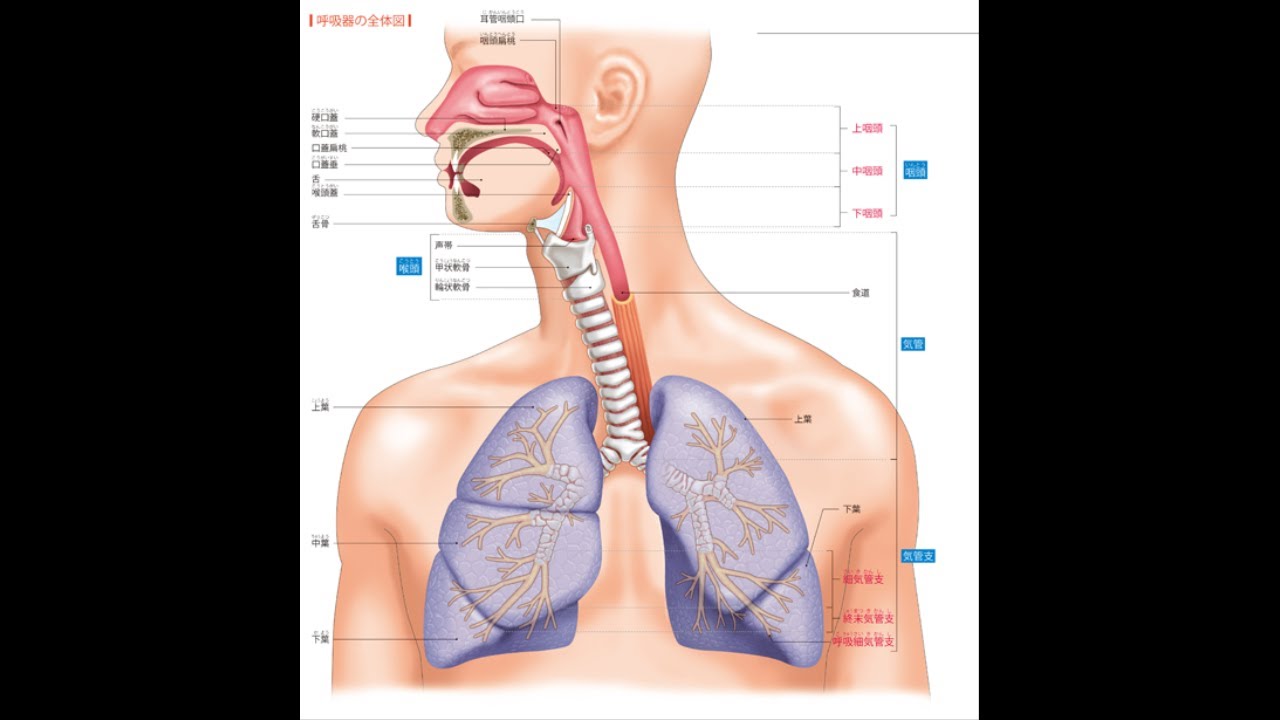剖検は、死体の死の原因を特定することを目的として、死体に対して組織的かつ階層的に行われる一連の手順と観察です。
「ネクロプシー」という言葉の語源は、ギリシャ語のnekros = 死体とopsis = 光景に由来しています。
臨床解剖
臨床剖検は病理医によって行われ、病気の病態生理学と病因を明らかにすることを目的としています。
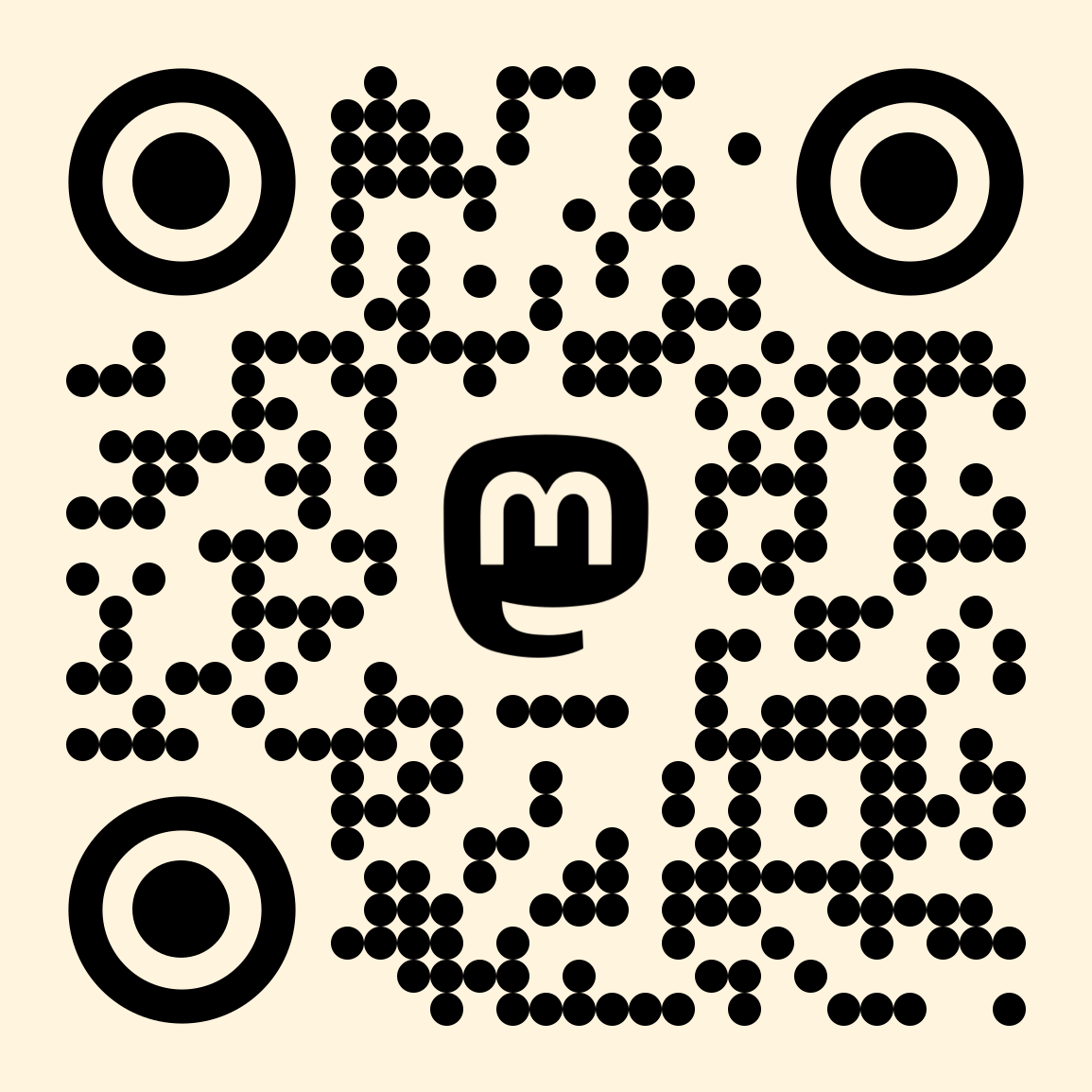
法医解剖
法医解剖は検視官によって行われ、個人の死に至ったメカニズム、影響、原因を解明することを目的としています。
動物の死後、その体に現れる変化を死体変化といいます。それらは、死後硬直、死後硬直、眼の変化、血液凝固、自己消化および腐敗です。
これらのプロセスは次のフェーズに分かれています。
- 死体の硬直。
- 死体の斑点。
- ガス状。
- 共謀;
- スケルトン化。
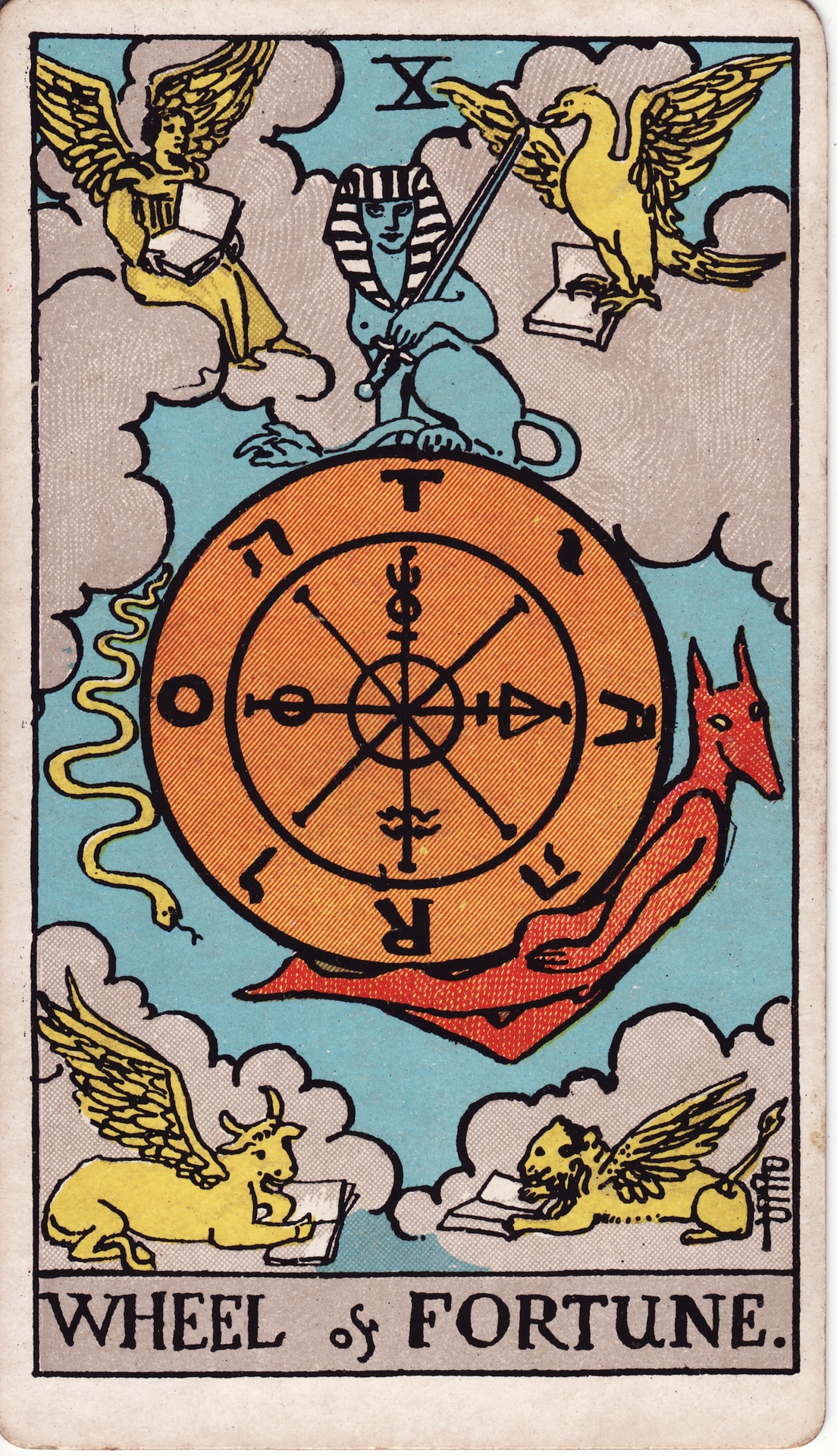
解剖×解剖
剖検と剖検は同じ意味で使用されてきました。 「オートプシー」という言葉は「自分の目で見る」という意味で、ギリシャ語のオートス(autos )=自分自身の、オプシス(opsis )=見るという言葉に由来しています。

参考資料
参考画像一覧


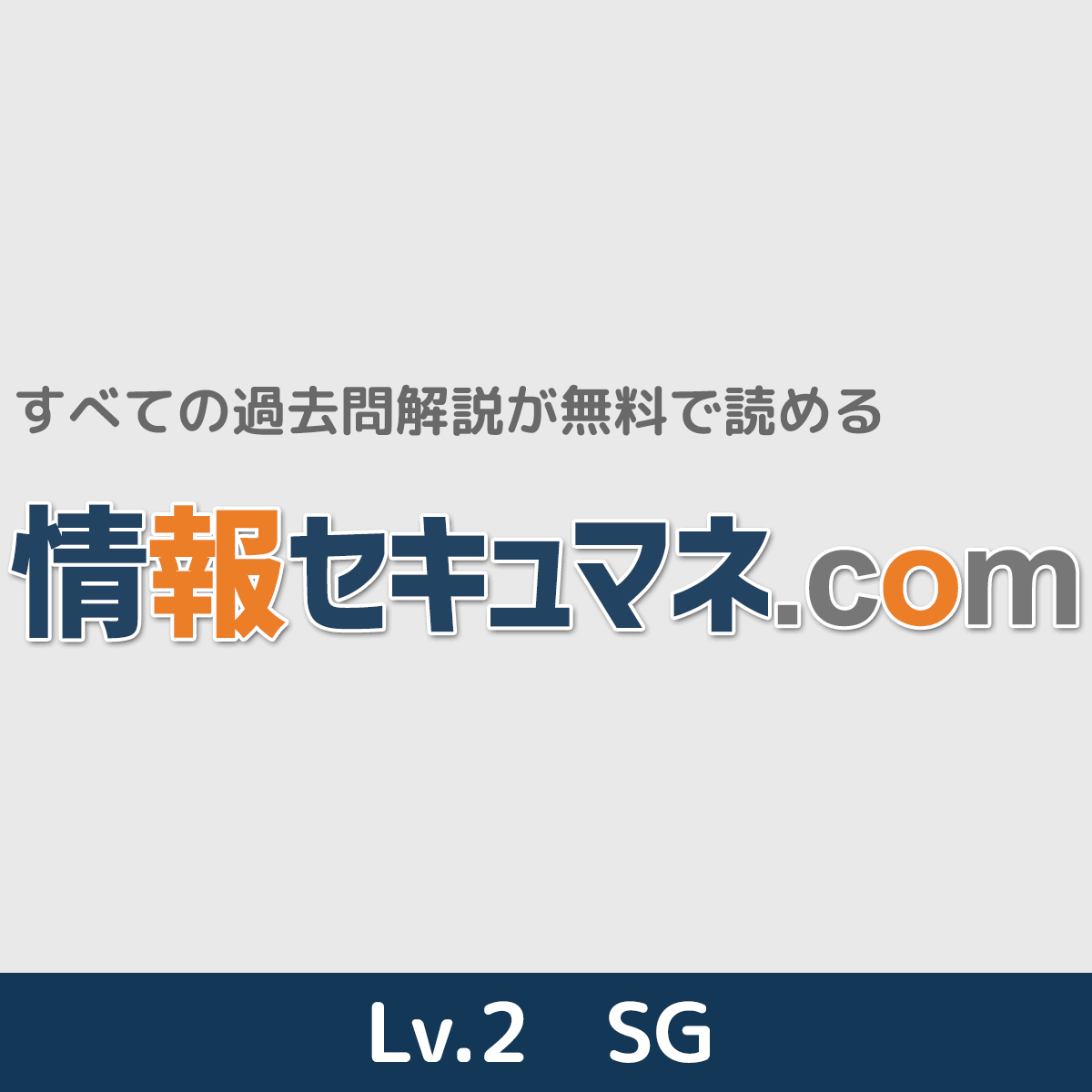



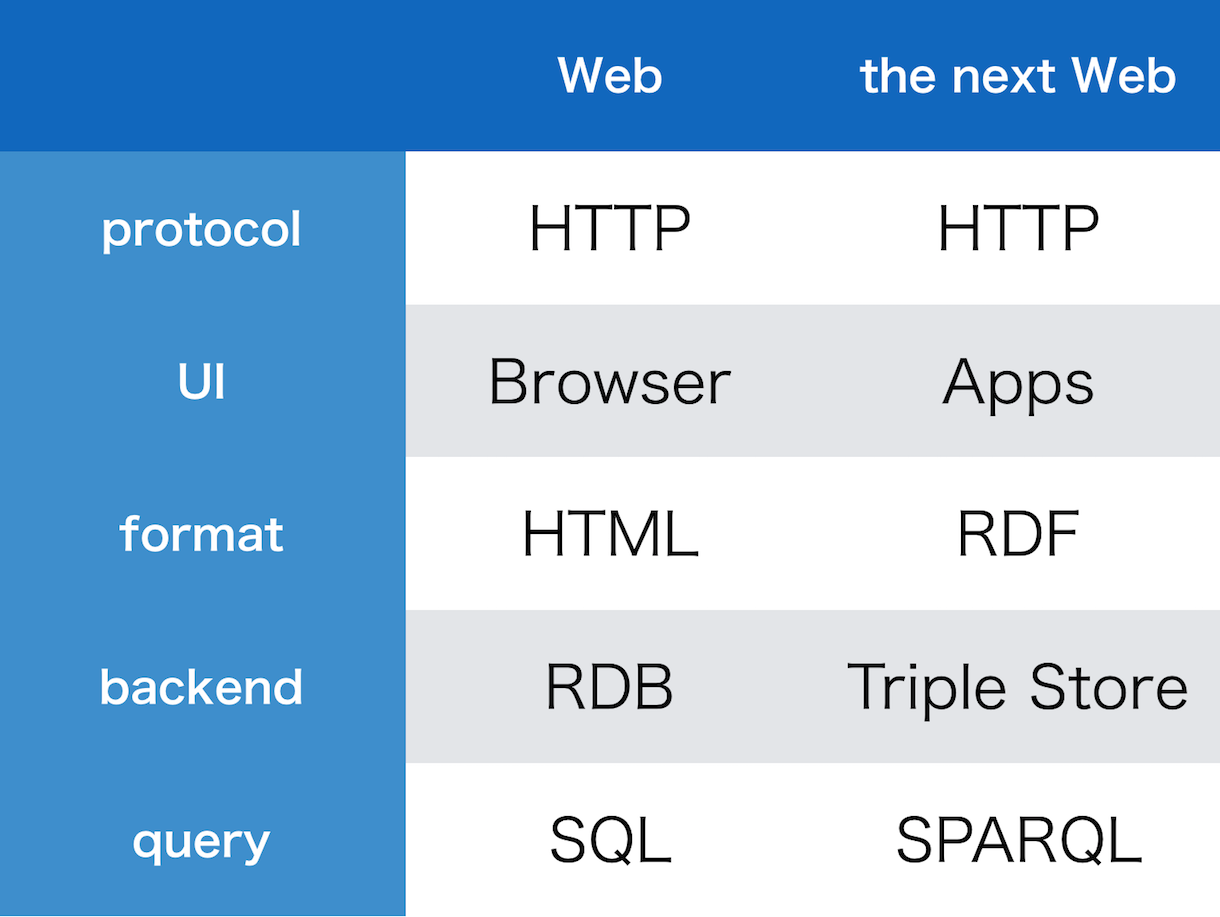
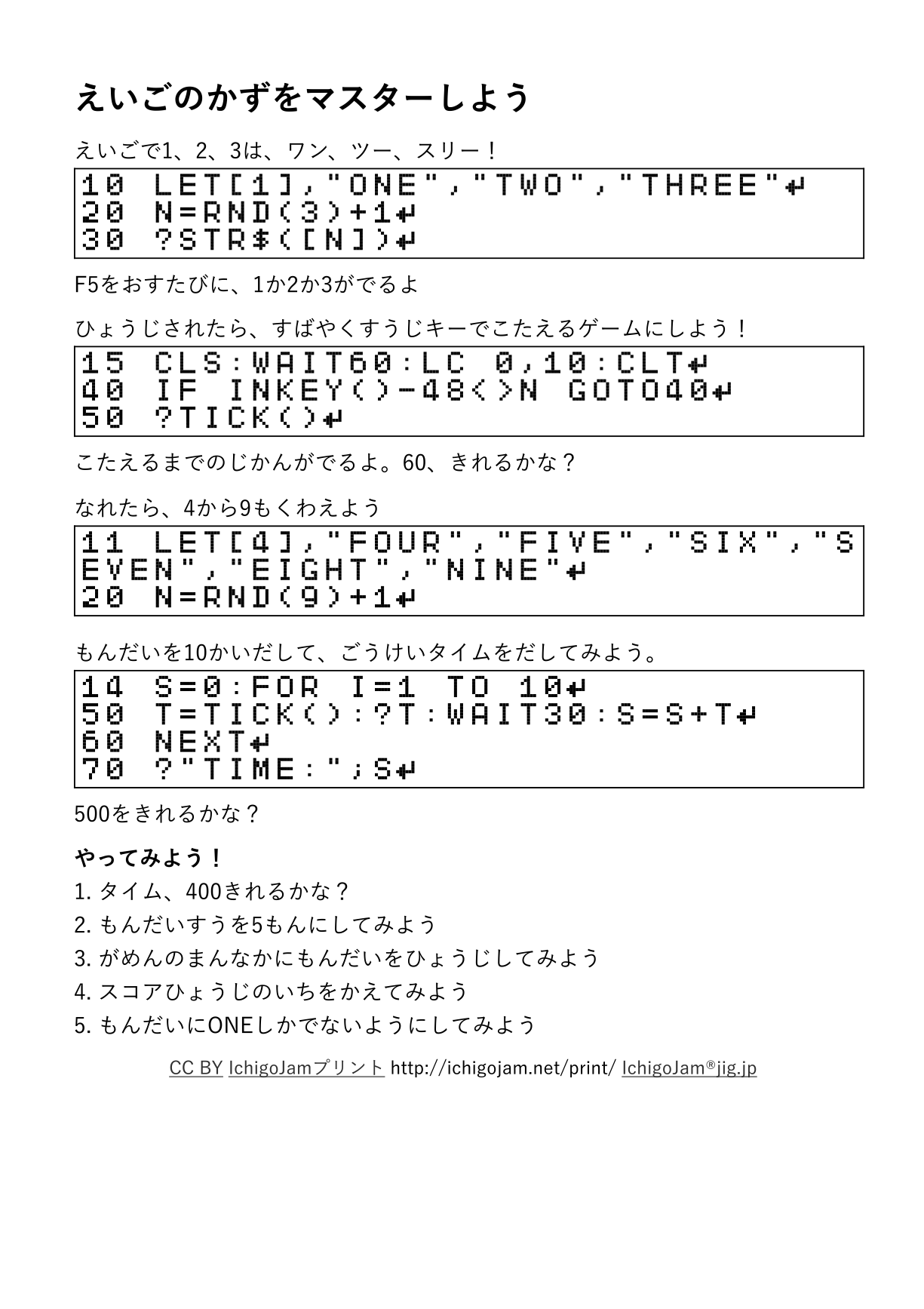

参考動画一覧
心房細動と言われたら知っておくべきこと【循環器専門医が6分で説明】
視覚伝導路と視野欠損の覚え方(PDF付き)
【感覚器系】嗅覚と味覚の仕組み
あまりに意味不明すぎる未解決事件の真相が判明した

.jpg?resize=1058,794&ssl=1)