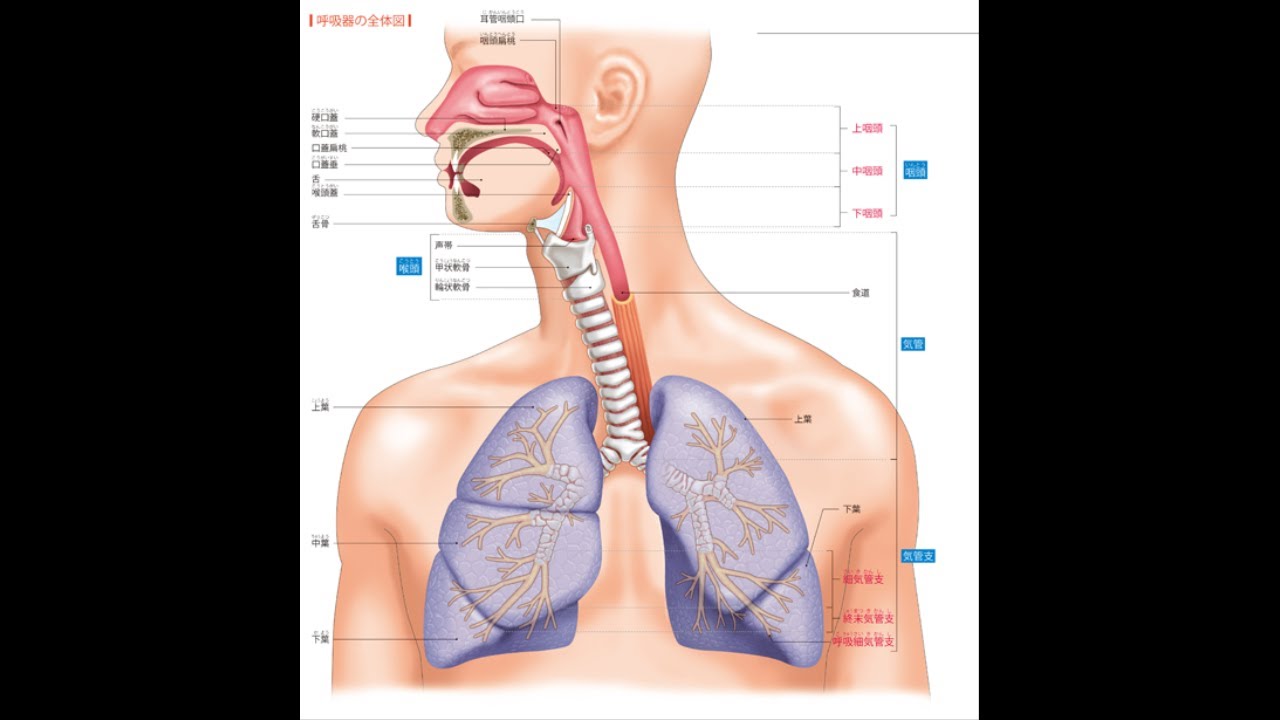憲法原則は、国の憲法に明示的または暗黙的に存在する価値観であり、法律全体の適用の指針となります。
憲法が法制度全体の基礎であることを考慮すると、憲法は法律のすべての分野に適用されるべきいくつかの原則を確立しています。
各法律分野に適用される最も重要な憲法原則を以下で確認してください。
憲法に適用される憲法の原則
憲法に適用される憲法原則は、連邦憲法第 1 条に規定されています。

主権
主権とは、国家が他の形態の権力に服従することなく、あらゆる側面(政治、法律、経済など)において自らを組織する能力です。国際舞台では、主権とは、ある国家が他の国家に従属しないことを指します。

市民権
市民権とは、直接的または間接的に国の政治組織に参加する個人の能力です。
人間の尊厳
人間の尊厳の原則は、法の支配が統治する民主主義国家において、政府の行動は国民がすべての社会的および個人的権利を完全に行使できることを保証しなければならないことを確立しています。
仕事と自由な企業の社会的価値観
この原則は、ブラジル国家が資本主義システムの特徴である企業と財産の自由を重視していることを指摘しています。
政治的多元主義
政治的多元主義は民主主義の基礎であり、国の政治組織への国民の広範かつ効果的な参加を保証します。

行政法に適用される憲法の原則
行政法に適用される憲法上の原則は、連邦憲法第 37 条に規定されており、次のとおりです。
合法性
行政法における合法性の原則は、他の法律分野で適用される原則とは逆の意味を持ちます。他の部門では、法律で禁止されていないすべてのことが許可されていますが、行政では、法律で禁止されていない場合でも、明示的な法律規定に従ってのみ行動することが許可されています。
非人格性
非人格性の原則によれば、行政は常に公共の利益のために行動しなければなりません。これを達成するには、公務員が個人的な便宜や特権を持たずに、自らが代表する公共団体を代表して公平に行動することが必要です。
道徳
公共の利益を追求するためには、行政行為は法律だけでなく、誠実さと誠実さにも基づいていなければなりません。
広告
行政は透明性のある方法で行動し、その行為、決定、推論への国民のアクセスを保証しなければなりません。このように、行政法における公共性の原則は、社会による行政の監視を保証するものである。
効率
効率性の原則では、行政行為は社会に対する目的を満足のいく効率的な方法で達成しなければならないと規定しています。さらに、公共団体の組織・体制においては、業務の分担と執行の適正化を図るため、効率性を発揮する必要がある。

訴訟法に適用される憲法の原則
連邦憲法は、手続き法に適用される次の原則を規定しています。
適正な手続き
適正な法的手続きは連邦憲法第 5 条 LIV に基づいています。これは、義務や保証を含め、法律で定められたすべての手順を伴う公正なプロセスを受ける権利をすべての人に保証する原則です。
適正な法的手続きは、手続き行為が有効、効果的、完璧であるとみなされるためには、法律で定められたすべての手順に従わなければならないことも定めています。
矛盾した広範な防御
相反する広範な防御の原則は、連邦憲法第 5 条 LV および民事訴訟法第 9 条および第 10 条に規定されています。
矛盾は、プロセスのすべての段階で被告に保証されている応答の権利です。広範な防御では、被告が応答を提示する際に、適用可能なすべての手続きツールを使用できることが保証されます。
アイソノミー
連邦憲法第 5 条第 1 章および民事訴訟法第 7 条に規定されているイソノミーの原則は、手続きにおける権利と義務の行使に関して、すべての当事者が平等に扱われなければならないことを定めています。
自然な裁判官
自然正義の原則は連邦憲法第 5 条 LIII に規定されており、所轄官庁以外は誰も訴追されず、刑を宣告されないことが規定されている。この原則は、裁判官の公平性を決定するだけでなく、裁判管轄規則にも反映されています。
管轄権の不可侵性
司法へのアクセスの原則とも呼ばれ、連邦憲法第 5 条 XXXV に規定されています。この原則によれば、権利が脅かされたり侵害されたりした場合は、法廷で議論することができます。
広告
公開の原則は、連邦憲法第 93 条 IX および民事訴訟法第 11 条および第 189 条に規定されています。同氏によれば、公共の利益に奉仕し、司法の監督を保証するには、無効という罰則の下で、手続き的行為は公開されなければならない(司法秘密が要求されるものを除く)。
セレリティ
手続きの合理的な期間の原則とも呼ばれ、連邦憲法第 LXXVII 第 5 条および民事訴訟法第 4 条に規定されています。この原則は、決定の有用性を確保するためにプロセスが合理的な時間内に完了する必要があることを確立します。

税法に適用される憲法原則
連邦憲法は、「課税と予算」というタイトルで、税法に適用しなければならない原則を規定しています。
合法性
税の合法性の原則は連邦憲法第 150 条 I に規定されており、事前の法的規定なしにいかなる連邦組織も税金を要求したり増額したりすることを禁止しています。
アイソノミー
連邦憲法第 150 条 II に規定されているイソノミーの原則は、同じ状況にある国民は納税に関して平等に扱われなければならないと定めています。
不遡及性
連邦憲法第 150 条 III「a」に規定されている行政非遡及規定は、税金を制定または増額した法律が発効する前に税金を課すことを禁止しています。
優先性
優先権の原則は、連邦憲法第 150 条 III、「b」および「c」に規定されています。同氏によると、連邦機関は税金を制定した法律の公布から90日以内に税金を課すことを禁じられているという。さらに、法律の公布と同じ会計年度(同じ年)に税金を徴収することは禁止されています。
没収の禁止
連邦憲法第 150 条 IV に規定されている没収の禁止は、税務当局が徴税を通じて納税者の資産を不当に占有することを禁止します。
交通の自由
交通の自由の原則は連邦憲法第 150 条 V に規定されており、公権力が維持する道路の料金徴収を除き、連邦機関が税金の徴収を通じて国民の往来の自由を制限することを禁止している。 。
貢献能力
連邦憲法第 145 条第 1 項に規定されているこの原則は、可能な限り、各個人の経済的能力に応じて税金を課すべきであると述べています。
選択性
連邦憲法第 153 条第 3 条 I に規定されている選択性の原則は、物品に課される課税はその本質に応じて変化しなければならないと規定しています。したがって、食料や燃料などの必需品は、タバコやアルコール飲料などの他の物品よりも低い課税対象となるべきです。

憲法の原則を刑法に適用する
合法性
刑法における合法性の原則は、連邦憲法第 5 条 XXXIX に規定されており、その存在を規定する以前の法律がなければ、犯罪や刑罰は存在しないと規定されています。
有利な法の遡及
刑法不遡及の原則としても知られ、連邦憲法第 5 条 XL に規定されています。この原則によれば、刑法は、その適用が被告にとって有益でない限り、発効前の事実には決して適用されない。
ペナルティの性格
連邦憲法第 5 条 XLV に規定されているこの原則は、いかなる刑罰も有罪判決を受けた被告の個人を超えてはならないと定めています。資産の損害または損失に対する賠償の場合、被告の後継者は、譲渡された資産の限度でのみ責任を負います。
文章の個別化
この原則は連邦憲法第 5 条第 XLVI に規定されています。同氏によると、有罪判決で適用される刑罰は、被告と事件自体の個別の状況を考慮して、事件に応じて個別に設定する必要があるという。

社会保障に適用される憲法の原則
社会保障に適用される憲法上の原則は、連邦憲法第 194 条のセクションにリストされています。
補償範囲とサービスの普遍性
この原則によれば、社会保障は、拠出金の直接支払いに関係なく、特に社会扶助と公衆衛生など、困っているすべての国民にサービスを提供すべきである。
都市部と農村部の住民に対する給付とサービスの均一性と同等性
均一性の原則は、社会保障の提供において都市部の住民と地方の住民の間で差がないことを規定しています。したがって、既存の差異は貢献時間、年齢、計算係数などの基準に基づく必要があります。
利益とサービスの提供における選択性と分配性
この原則は、社会保障給付の付与は選択的でなければならないと述べています。したがって、国民が希望する保険を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。さらに、すべての事象をカバーすることは不可能であることを考慮して、選択性の原則により、立法者は、カバーを提供するためにより緊急性と保護に値するリスクと状況を特定する必要があると規定されています。
利益の価値の還元不可能性
還元不可能性の原則は、国民が自らの利益の名目価値を減額されない権利を保障するものである。
資金調達への参加という形での株式
この原則は、同じ経済状況にあるすべての納税者が平等に社会保障に貢献しなければならないことを確立しています。
資金調達基盤の多様性
連邦憲法第 195 条に規定されているこの原則は、社会保障が社会全体とすべての連邦組織からの資金によって資金提供されることを規定しています。

デリケートな憲法原則
憲法上の機密原則は、連邦憲法第 34 条第 7 条に規定されている価値観であり、これに違反した場合、違反に責任のある加盟国に対する連邦政府の介入が生じます。
デリケートな憲法上の原則は次のとおりです。
- a) 共和制の形態、代議制および民主主義体制。
- b) 人権。
- c) 地方自治。
- d) 直接的および間接的な行政の説明責任。
- e) 州税(移転から生じるものを含む)から生じる最低限必要な収入を、教育および公衆衛生活動およびサービスの維持および発展に適用する。
以下も参照してください。
参考画像一覧








参考動画一覧
【ゆっくり政治学講座】番外編:憲法とは何か
【憲法】法律初学者向け!憲法の存在意義と国民主権、基本的人権を理解する!
【憲法改正①】問題の基礎知識を中田がわかりやすく解説
日本国憲法の3つの原則